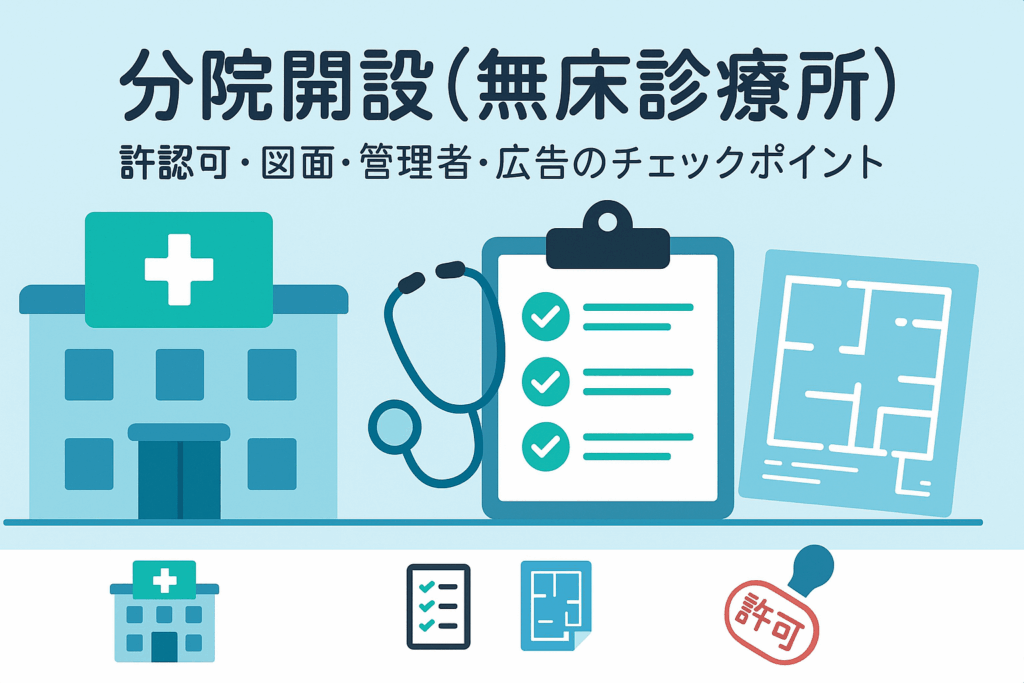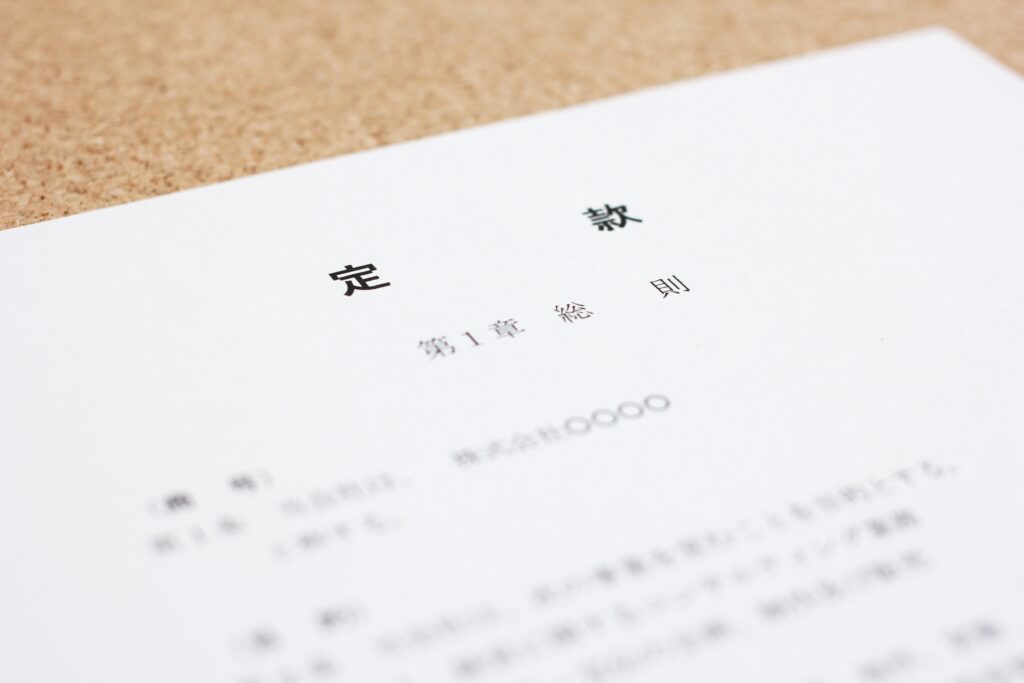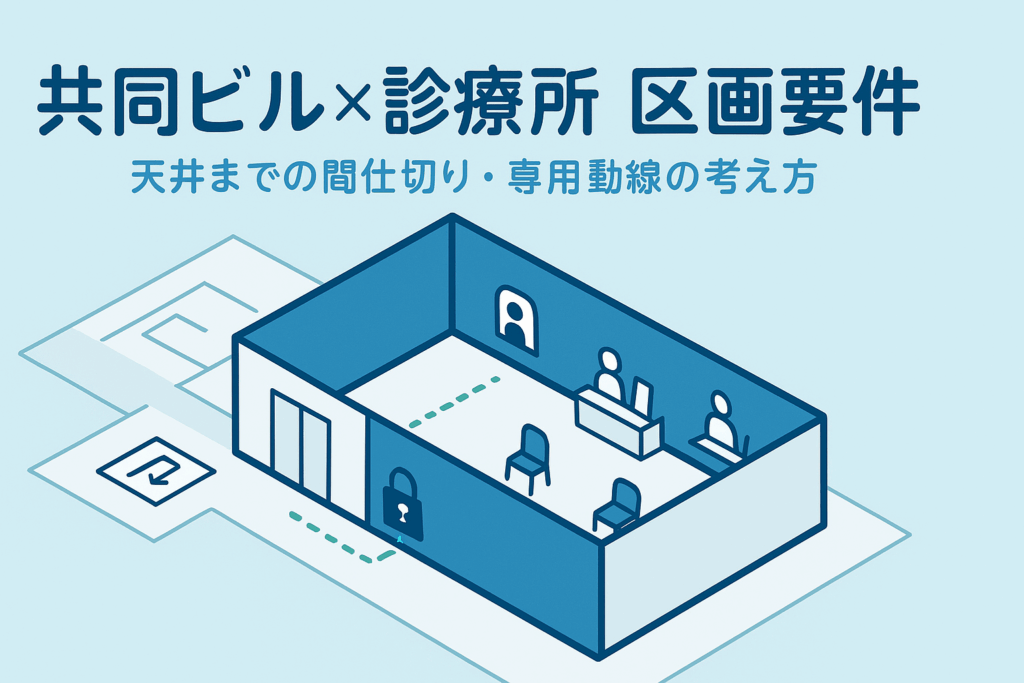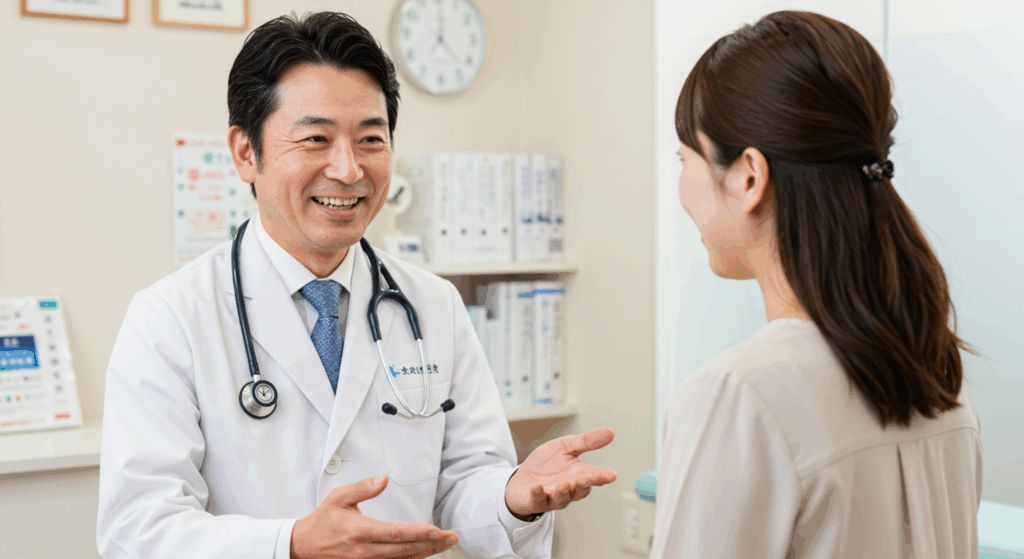
はじめに
まず位置づけです。
医療広告は「患者の適切な選択」を守るため、原則として広告できる事項を限定し、それ以外は不可とする仕組みです。
医療の内容については客観的評価・事後検証が可能な事項に限るという考え方が貫かれています。
他方、医療に関する表示は景表法や医薬品医療機器等法とも重なり得るため、これらの法令とも有機的に連携して運用されます。
「広告」に当たるか(定義・対象)
広告該当性は
①受診等を誘引する意図(誘引性)、
②医療機関や医師等が特定可能(特定性)の両要件で判断します。
新聞記事などは通常①を満たさず広告ではありませんが、医療機関が自サイトに体験談を載せる場合は広告に当たる点に注意です。
「これは広告ではない」等の断り書きがあっても、実質的に①②を満たすなら広告として扱われます。
媒体は紙・看板・放送・ウェブ・メール・口頭説明会等が含まれます。
一方で学術論文・通常の新聞記事・院内掲示・職員募集は、通常は広告と見なされません(ただし“記事風広告”や誘引目的の体験談の肩代わり掲載は別)。
禁止される広告(代表例)
(a) 虚偽広告:医学的にあり得ない断定、加工した術前後写真、根拠なき満足度表示等は不可です。
(b)比較優良広告:自院が他院より優れている旨や「日本一」「最高」など最上級表現は、事実であっても禁止されます。
(c)誇大広告:事実の不当な誇張や誤認を与える表示(費用の見せ方、根拠薄弱な“おすすめ”表現等)を含みます。
(d)体験談:患者等の主観や伝聞に基づく効果体験の紹介は広告不可。SNSや口コミでも、医療機関の関与(費用負担等)があれば広告と評価され得ます。
(e)ビフォー・アフター:誤認のおそれがある術前後写真は不可。自由診療では、治療内容・費用・主なリスク等を明確に併記し、分かりやすい場所に掲載するなど一定条件を満たす場合は例外的に許容されます。
(f)広告可能事項以外:例えば「専門外来」「死亡率・生存率」「未承認医薬品による治療」等は広告不可です。
広告できる事項と表現
広告可能事項は、医療法・告示が定める包括規定(診療科名、所在地、管理者、設備・人員、連携、情報提供体制、提供医療の内容等)に沿います。
どの項目をどう書けるかはガイドライン本文の該当条項で詳細に整理されています。
「限定解除」(ウェブ等での拡張)
患者が自ら求めて入手する情報については、条件を満たせば広告可能事項の限定を解除できます。
具体的には、
①患者が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等であること、
②問い合わせ先等を明示すること、
③自由診療の治療内容・標準的費用等を提示すること、
④自由診療の主なリスク・副作用等を提示すること、
全てを充足する必要があります(③④は自由診療に限る)。
規制対象者と他法令
広告規制の対象は医療機関に限られず、広告代理店・メディア・アフィリエイター・一般人等「何人」も含まれます。
掲載・放送に際して違反内容があれば、依頼者と並び指導対象となり得ます。
海外事業者による国内向け広告も対象です。
また、医薬品医療機器等法は虚偽・誇大や未承認品の広告を禁じており、医療広告の運用とあわせて適用されます。
実務ポイント(チェックリスト)
① 掲載内容が広告可能事項に該当するか、根拠(統計・資格・件数等)が即時提示できるかを確認。
② 自由診療の紹介は、費用・リスク・副作用の明示と問い合わせ先表示を徹底(限定解除①~④)。
③ 体験談・ビフォーアフター・最上級表現・キャンペーン強調は使わない(違反典型)。
④ 監督当局の相談・指導・公表手順も想定し、記録化と更新体制を整える(第6章)。
以上を押さえれば、「患者の適切な選択に資する、正確で検証可能な情報提供」を中核に、ウェブやSNSを含む現代的な媒体でも適法・適切な広報運用が可能になります。