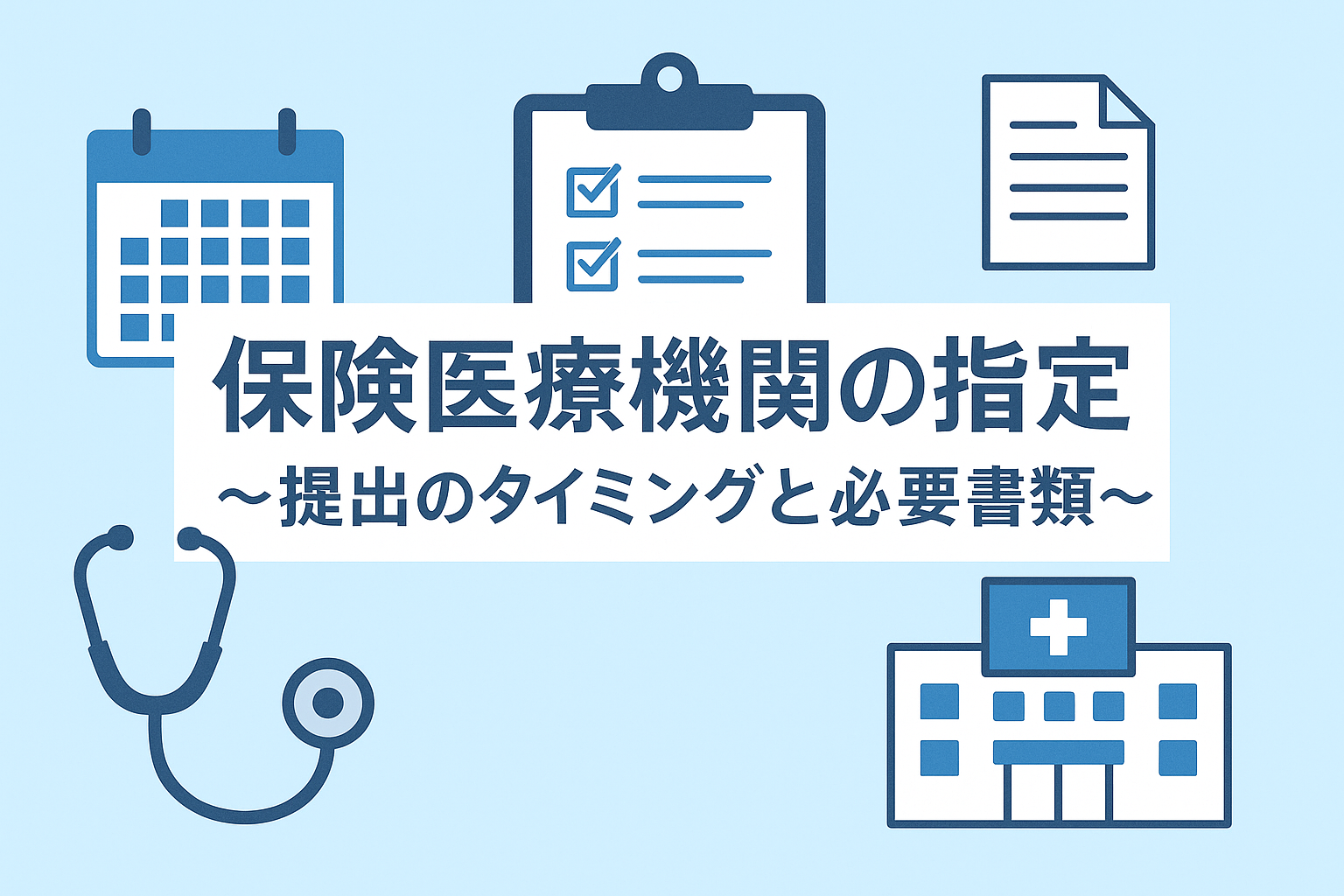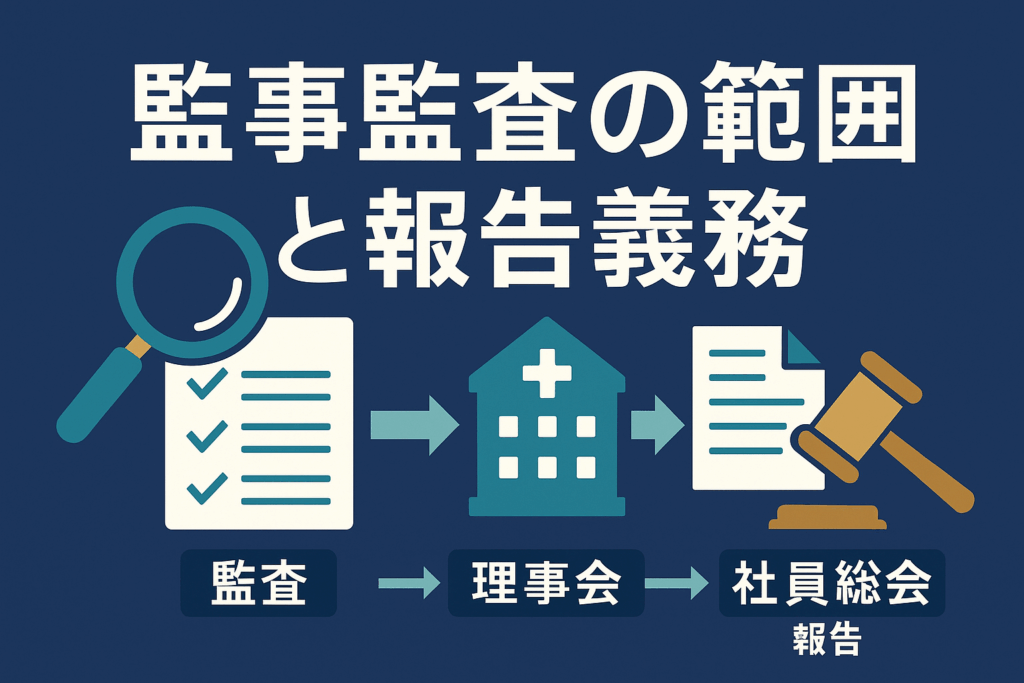
はじめに
医療法人のガバナンスで、監事は最後の安全弁です。
とはいえ「何をどこまで見て」「どこに報告するのか」が曖昧だと実効性が出ません。
今回は医療法の趣旨に沿って、監査の射程と報告ラインを実務目線で整理します。
監査の“対象”は2本柱
監事が見るのは、①業務の執行(理事会運営・意思決定プロセス・利益相反手続 等)と、②財産の状況(会計処理・資金繰り・固定資産・内部牽制)の二本柱。
数値の正確性だけでなく、手続の適法性と合理性までを点検するのが肝です。
資料入手は理事長経由に限られず、必要な帳簿・書類・現場へのアクセスが前提になります。
監査の“方法”はリスクベースで
全件チェックは非現実的。
金額の大きい取引/関連当事者との取引/現金・在庫等の不正リスク領域を厚めに見るリスクベース監査に切り替えましょう。
会計だけでなく、理事会議事録・招集手続・決議の有効性(定足数・特別決議要件)を、原議資料まで遡って照合すると、形式だけの承認を見抜けます。
監事の“独立性”は絶対条件
監事は理事や職員との兼務が不可。
また、理事長の親族など実質的な利害関係にも注意が必要です。
独立性が損なわれると、監査の正当性も吹き飛びます。
選任時は利益相反の有無・専門性・時間確保をチェックリスト化しておきましょう。
“報告義務”の正しい順番
① 定期報告:会計年度ごとに監査結果を理事会へ報告し、その要旨が社員総会(又は評議員会)で説明されるのが基本線。
② 随時報告:法令・定款違反や重大な不正の疑いを認識したら、速やかに理事会へ是正を促す報告を行います。
改善が見られない場合は、社員(社員総会)に注意喚起し、必要に応じて所轄庁からの指導・報告徴収のルートを意識(実務では、記録化→外部専門家助言→臨時理事会招集の順で対応)。
③ 議事録への関与:理事会・総会で監事が述べた意見は議事録に明記。
これは後日の説明責任(アカウンタビリティ)の核になります。
よくある“落とし穴”と回避策
① 会計だけを見る:→理事会手続・公告・認可申請のプロセスも必ず点検。
② 証跡が残らない:→監査計画・実施記録・指摘事項・是正確認まで書面化。
③ 関連当事者取引の見落とし:→理事・近親者・関係会社の取引台帳を作成し、理事会承認と事後報告の有無を突合。
④ 内部統制の“名ばかり”運用:→支出権限表・押印権限・二重承認の実在性をサンプル検証。
⑤ 監事1名に過負荷:→外部専門家のスポット支援(会計・法務)でピーク時を補完。
年間サイクル
① 年度初:リスク評価→監査計画・重点領域を理事会へ共有
② 四半期:重要取引・関連当事者・資金繰りのレビュー
③ 決算期:決算書・事業報告・附属明細の突合/監査報告書案作成
④ 総会前:理事会へ最終報告→社員総会で要旨説明/指摘事項の是正計画を付帯決議に
監事から見た“良い法人”の条件
① 重大取引は理事会で事前審議、利益相反は当事者除斥が徹底。
② 議案・根拠資料・決議・執行が一本の証跡でつながる。
③ 監事の指摘に期限付きアクションプランで応える文化がある。
まとめ
① 監査の範囲=業務+財産の二本柱を押さえたか
② リスクベースで重点領域を定め、証跡を残したか
③ 理事会→社員総会の報告ラインを踏んだか(随時報告含む)
④ 独立性・利益相反の管理は万全か
⇩