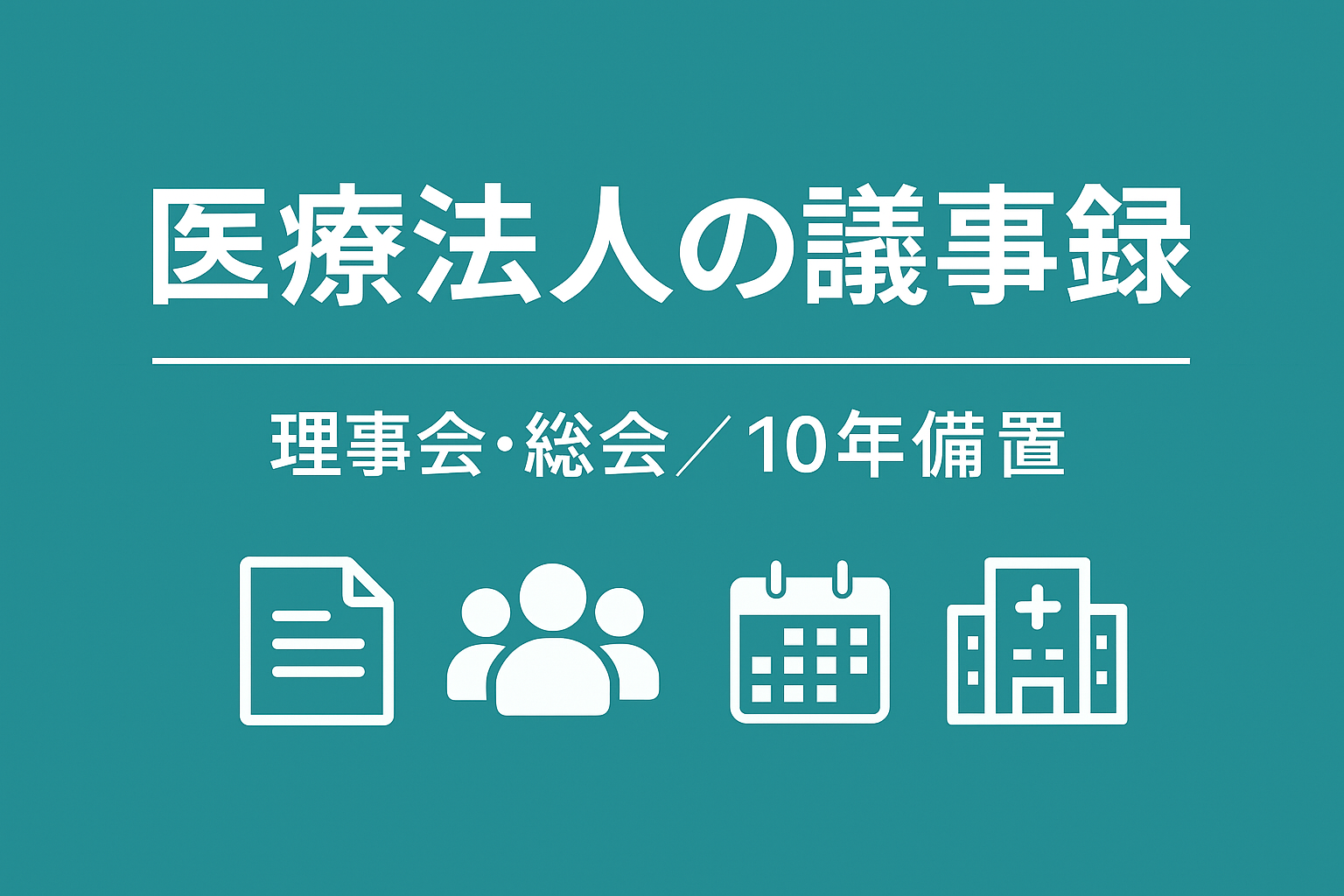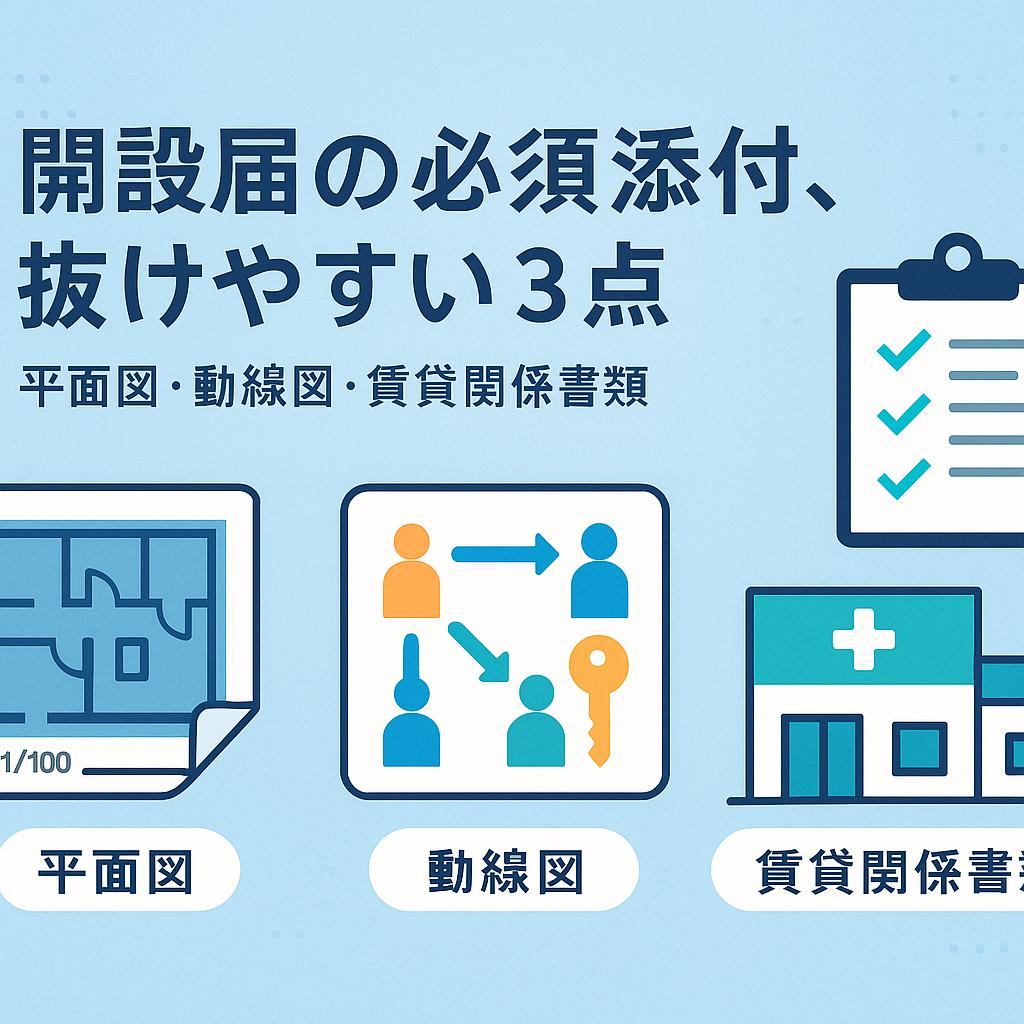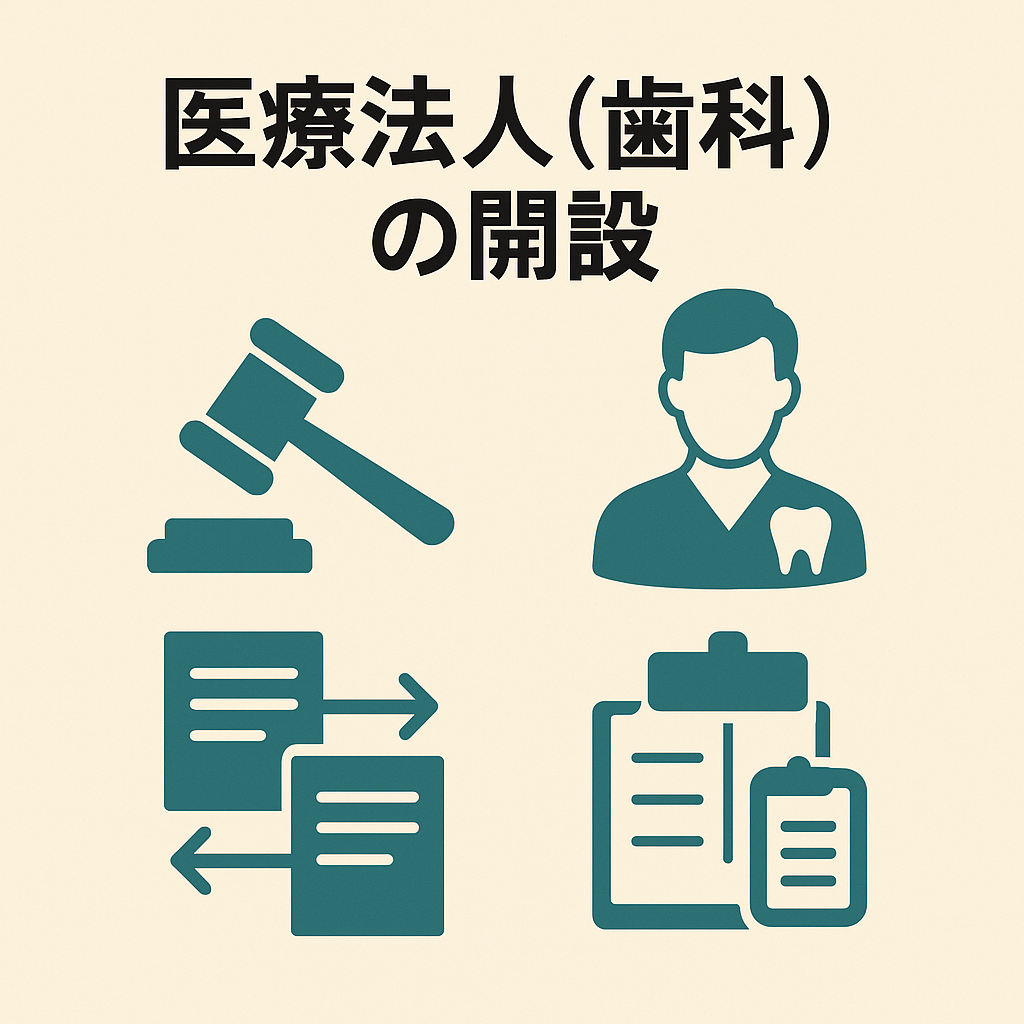
はじめに
歯科診療所を医療法人で開設するご相談は、近年とても増えています。
本稿では、実務の要点を行政書士の視点で、手続きとガバナンス(統治)を両輪で整理します。
結論と基本姿勢
医療法人で歯科を開設する際の審査は、①開設・経営の責任主体が内部に実在していること、②非営利性(剰余金不配分・取引の適正)が担保されていること、の二本柱が基礎です。
歯科固有の核は管理者=歯科医師。病院は常勤必須、診療所でも指揮命令系統を明文化し、任命書・職務分掌・不在時代行まで整えておくと審査が滑らかです。
手続フロー(前倒しが肝心)
①定款整備:目的・業務に「歯科診療所の開設・運営」を明記(必要に応じて附帯業務も)。
②会議体決議→所轄庁手続:社員総会(社団)等の特別決議を経て認可・届出。
③図面・人員・規程の統合資料:X線室の遮蔽計画、感染対策、勤務表、個人情報・医療安全規程を一冊化。
④保健所→厚生局:開設許可・届出、管理者任命、レセ電申請、保険医療機関の指定へ。
クリティカルパス(定款→所轄→保健所→厚生局)で逆算し、採用・研修と同期させます。
ガバナンスの設計(疑義を生まない四点固定)
実体:理事会規程・職務権限・稟議フロー・印章管理を整備し、人事・契約・資金の最終決裁が法人内部にあることを文書で固定。
契約:支援会社・家主等との契約に、外部が意思決定を左右する条項を入れない。価格は相場妥当性(独立当事者原則)で説明可能に。関連当事者取引は理事会で利益相反手続を運用。
表示:院内掲示・HP・帳票を「開設者名/管理者(歯科医師)氏名」で統一。
証跡:議事録・決裁ログ・押印台帳・関連当事者台帳を体系化し、照会に即応。
理事体制の小規模特例
原則は理事3名以上・監事1名以上。ただし医師・歯科医師が常時1〜2人勤務する診療所を一か所のみ開設する小規模法人は、知事認可で理事3名未満も可とされています。
もっとも実務上は「可能な限り理事2名が望ましい」運用が一般的。
牽制と継続運営の観点から、2名体制+独立した監事を基本線に設計するのが賢明です。
歯科特有の留意点
X線室は遮蔽・標識・点検記録までを図面+手順書で説明。感染対策は滅菌導線や手洗い設備の配置を明確化。
自費診療の表示は医療広告ガイドラインに整合させ、体験談・ビフォーアフター・比較表現の扱いをルール化。
技工・読影等の外部委託は責任分界とデータ帰属を契約・SOPで明記し、定期的な品質監査の記録を残しましょう。
開設後は事業報告・計算書類・財産目録の備置・届出を期限管理し、監事監査→理事会報告→是正のPDCAを年次で回します。
まとめ
歯科で医療法人を開設する要所は、①「責任主体の実在性(人事・契約・資金の最終決裁が法人内にあること)」、②「非営利性(剰余金不配分・関連取引の相場妥当性)」、③「管理者=歯科医師の体制と表示の一貫性」、④「小規模特例の正確な適用(理事数・監事の独立性)」の四点です。
これらを“定款・会議体運用・契約・表示・証跡”で噛み合わせ、保健所→厚生局までのクリティカルパスを逆算すれば、開設後の運営も安定します。
医療専門行政書士は、このような行政手続きをサポートし、歯科の先生方の良き伴走者としてお手伝いをさせていただきます。