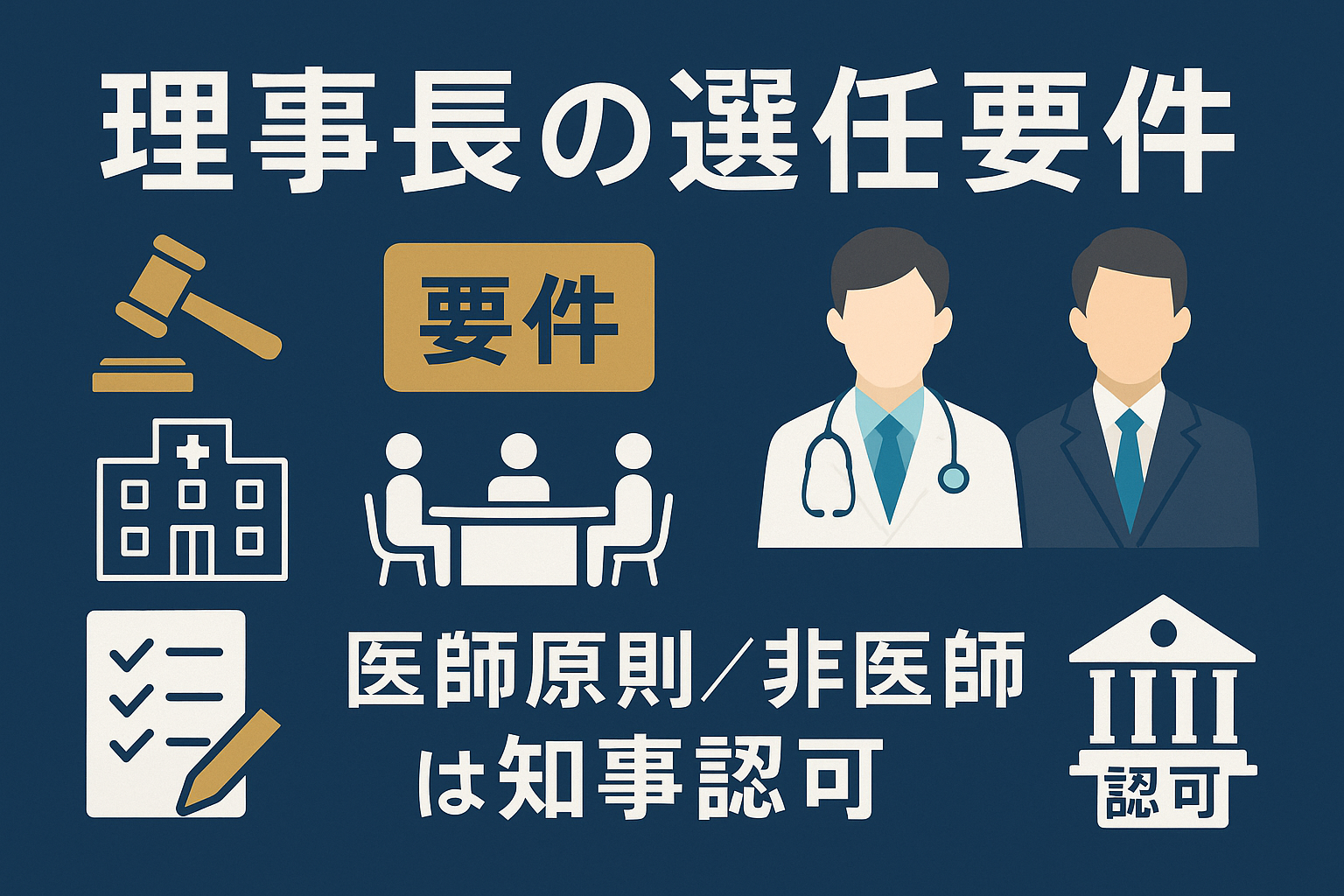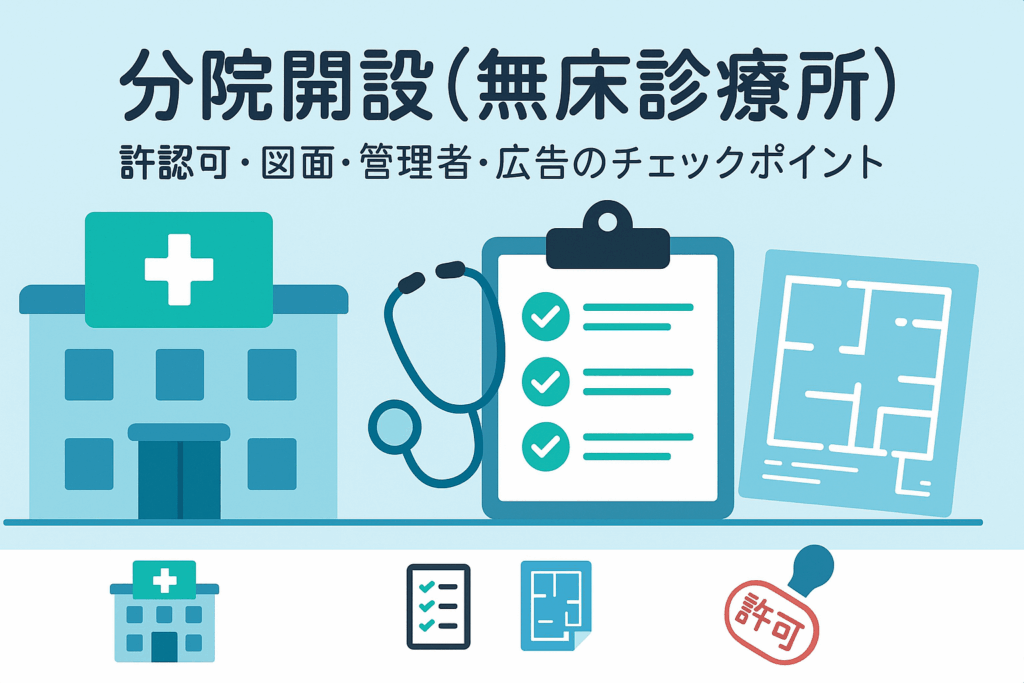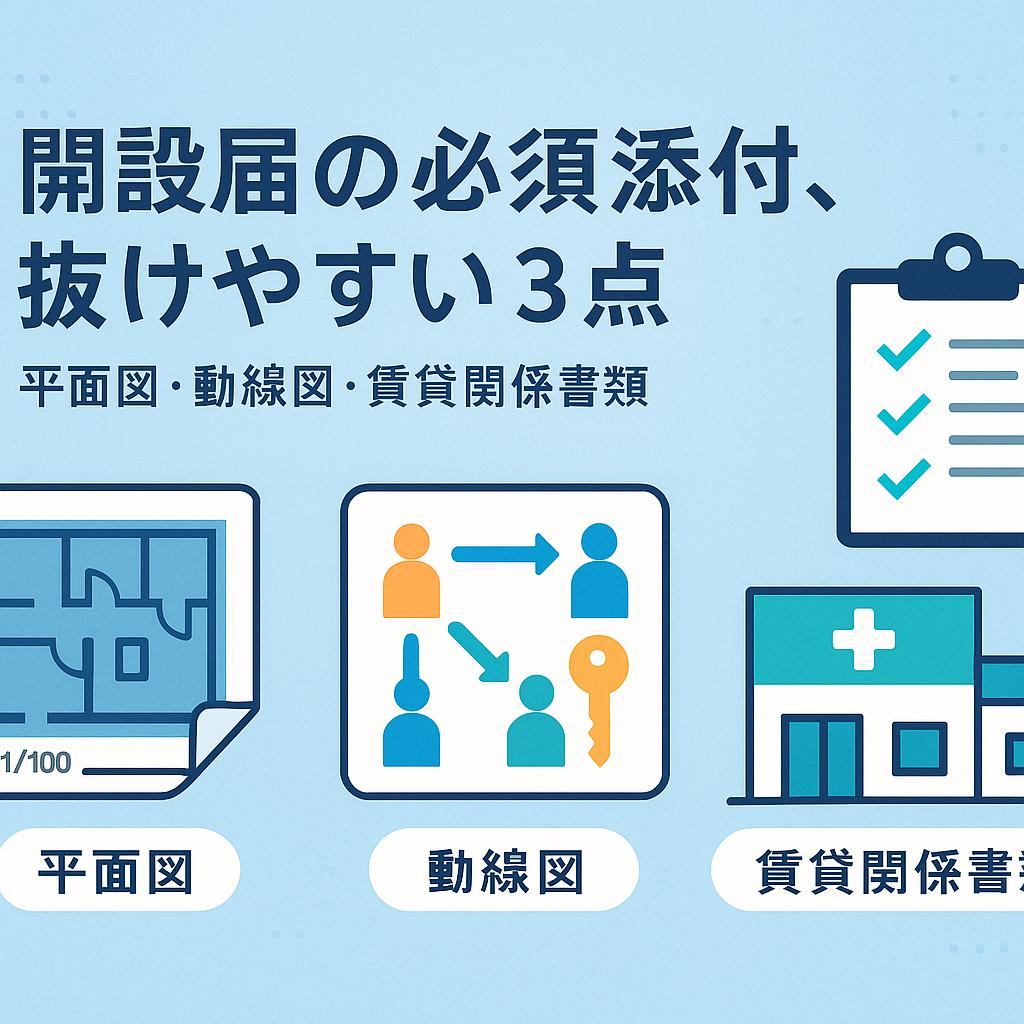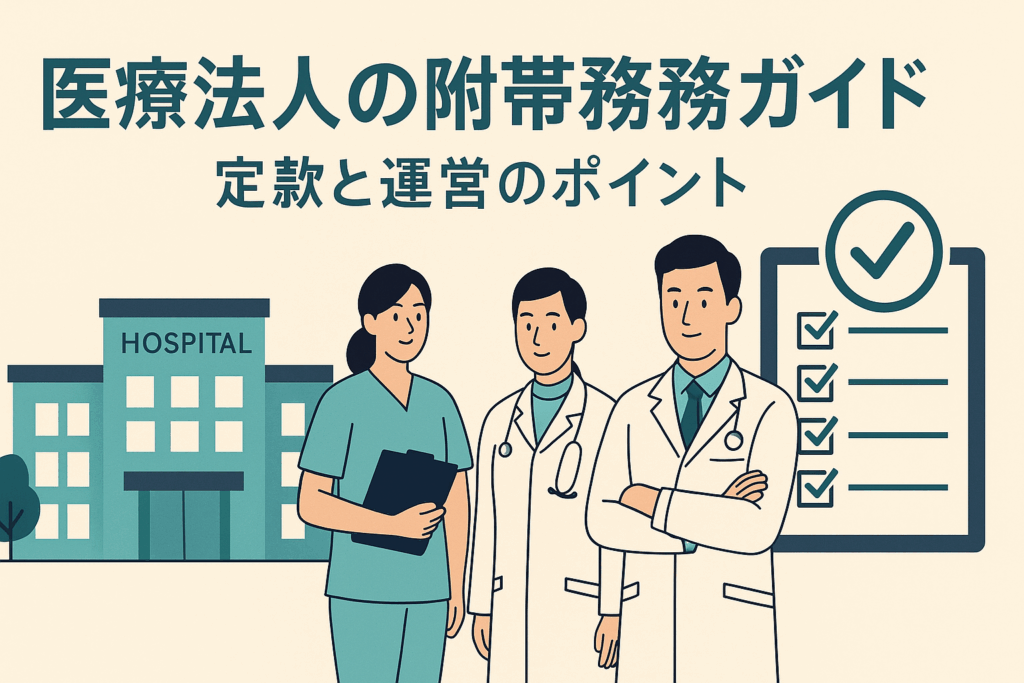
定義と法的根拠
医療法人は、本来業務(病院・診療所・老健・介護医療院の運営)に「支障のない限り」、定款(寄附行為)の定めに従って医療法第42条各号の業務=附帯業務を行えます。
附帯業務のみの運営や、附帯業務の全面的委託は“不適当”と明示されています。
附随業務との違い
院内売店や敷地内駐車場、当該病院⇄患者の自宅の無償搬送などは「附随業務」にあたります。
これは収益業務に含まれず、定款変更も不要です。
一方、敷地外の遊休地での駐車場や、他院⇄他院への搬送は附随に含まれません。
附帯業務の“許容基準”
附帯業務は次の基準を満たす必要があります。
①社会通念上、医療法人の業務として認められる程度である。
②社会的信用を傷つけない(例:風俗営業、武器製造、遊戯場は不可)。
③投機的でない。
④本来業務の円滑な遂行を妨げない。
⑤名義貸与など不当な方法でない。
代表例
医療関係者の養成・再教育(看護・リハビリ等の養成施設や再研修)、医学・歯学研究所の設置、疾病予防や健康教育に関する事業、高齢者・母子保健関連、各種検査・養成事業、そして介護保険・障害福祉サービス等が挙げられます。
介護・障害サービスと「移送」の扱い
介護保険・障害福祉サービスを附帯業務として実施する際、当該サービスと「連続して」又は「一体として」行う有償移送は附帯業務に含め得ると整理されています。
非営利性と収支管理
医療法人は営利を目的としない法人です。
附帯業務で得た収益も含め、法人の目的達成(医療・介護の提供)に充てられる体制が必要です。
開設許可・監督実務でも「開設者が非営利で、開設・経営の責任主体たり得るか」を厳正に確認するよう示されています。
① 定款どおりの業務だけを行う
附帯業務は定款(寄附行為)に明記された範囲で実施します。
記載のない業務は行えません。
「定款に記載のある業務が行われ、記載のない業務は行われていないか」を確認対象とし、違反時は中止指導や定款変更を求める取扱いです。
② 本業優先の原則
附帯業務の経営が主たる医療・介護事業に支障を来さないことが大原則です。
人員配置・時間外労務・設備利用などの観点で、本業に影響が出ない計画かを事前に点検します。
③ 休止・未実施の扱い
定款に掲げた業務を休止・廃止する場合は、方針の確認と定款変更等の手続が必要です(やっていない業務を放置しない)。
④ 形だけの運営は不可
医療法人が自ら病院等を開設せず、指定管理者として管理のみを行う形は認められません(実質的な開設・運営責任を負う体制が必要)。
定款・認可の実務
附帯業務は、原則として定款(寄附行為)に明記し、都道府県知事の認可(定款変更認可)を経て実施します。
なお、既に定款に掲げた附帯業務と「同一の事業」を新たな事業所で行うだけなら、定款等の変更不要とする取扱いが示されています。
禁止・留意(ガバナンス)
本来業務を開設・運営せずに附帯業務だけを行う、附帯業務を外部に丸投げする、社会的信用を害する事業に踏み込む、これらは不可にあたります。
まとめ(導入前のチェックリスト)
• 【定款】業務名・根拠条号・対象・実施体制を明記する草案を作成
• 【本業優先】人員・資金・施設利用が本来業務を圧迫しない試算
• 【制度横断】介護・障害・運送など“個別法”の許認可・登録要否の洗出し
• 【運営手段】委託の可否・範囲は「附随」「附帯」で要件が異なる点を確認
• 【内部統制】名義貸与・利益相反・投機性の排除、情報公開の手順化
以上を押さえ、「定款整備→認可→個別法手続→運営監査」の順に進めるのが、法令遵守と地域貢献を両立させる最短ルートです。