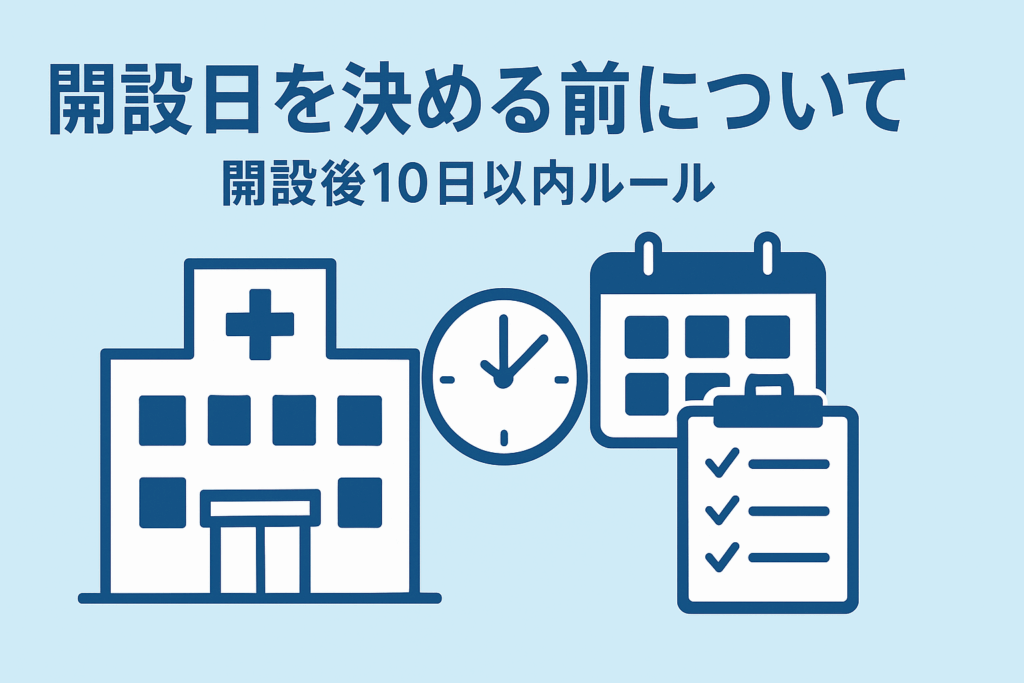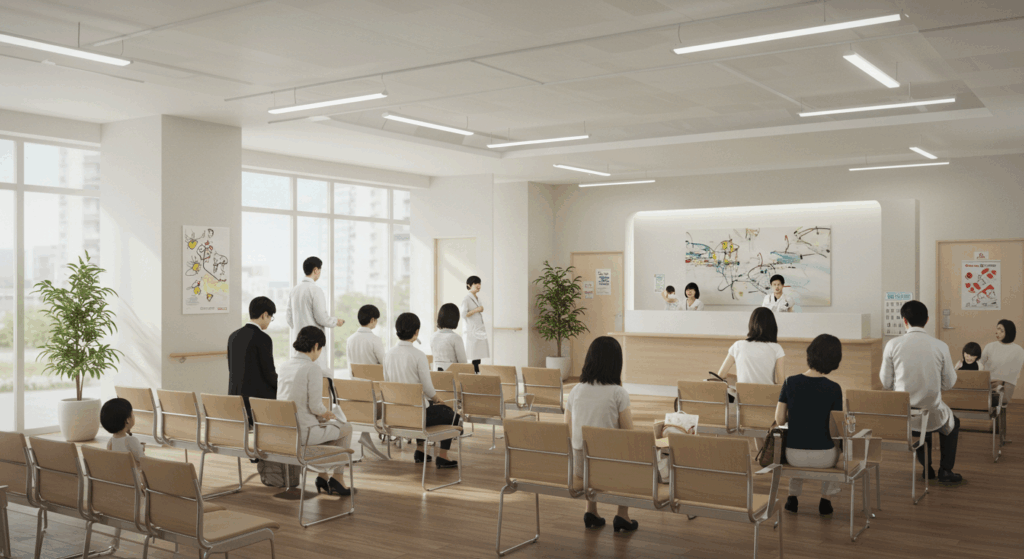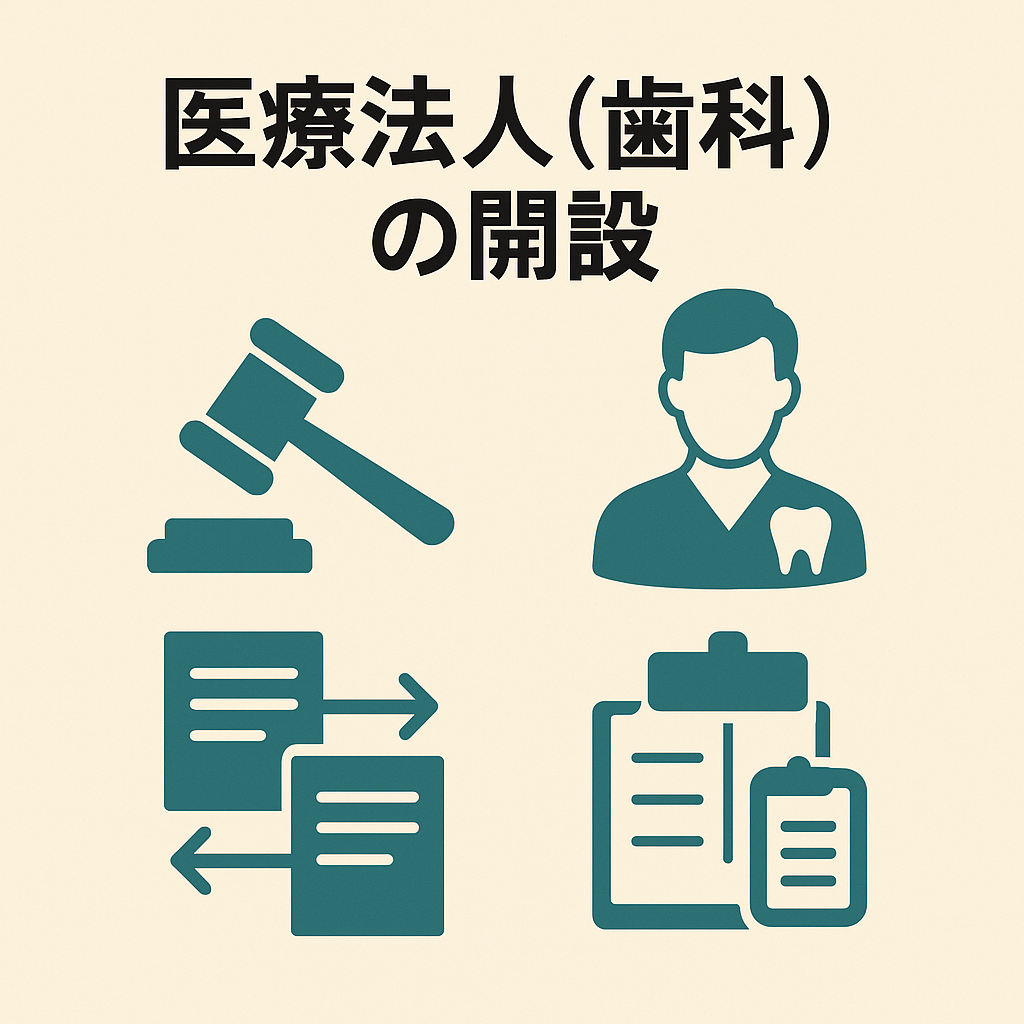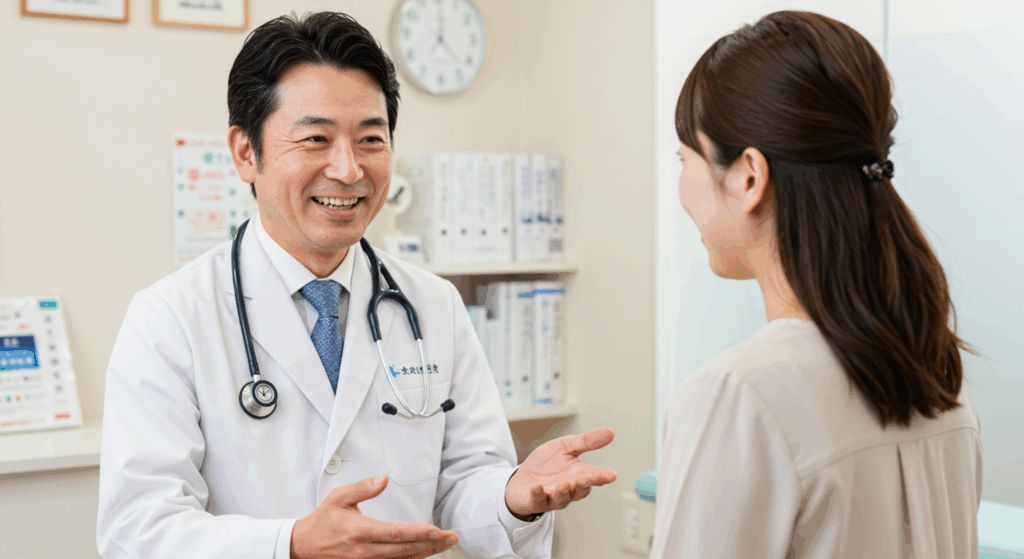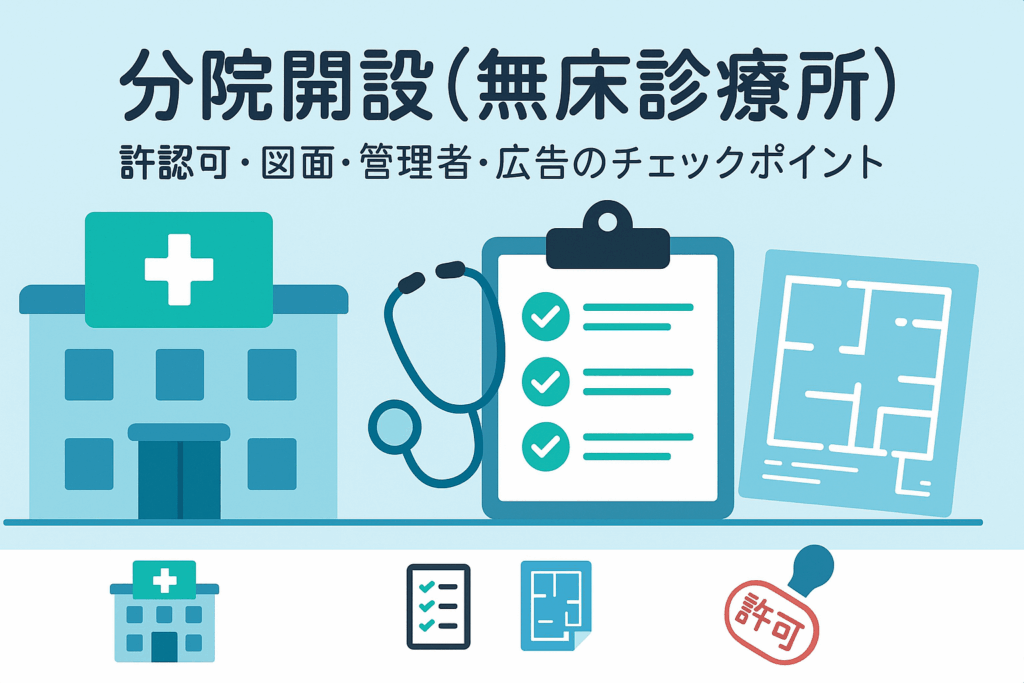
はじめに
分院開設は、物件探しや人材採用から始めたくなりますが、実は先に「医療法に合う設計」を固めてから動くほうが早く、安全です。
ここでは無床の診療所として分院を出す前提で、医師の方にも読みやすい順番で要点を整理します。目的は、許認可を滞りなく通し、開設後も安心して運営できる“型”をつくることです。
まず“無床の診療所”として手続きを固定
医療法人が分院(無床診療所)を出すときは、原則として医療法7条の「許可」を受け、そのうえで開設後10日以内に8条の「開設届」を行う流れになります(医師個人開設は8条届出のみ)。
計画段階から保健所へ事前相談を入れ、標榜科・診療時間、平面図(待合/診察/処置/X線/薬品保管)、設備リストを持参して“図面段階で適合”を取り切るのがコツです。
自治体の手引・様式に沿って〈事前相談→設計調整→許可申請→工事→開設前確認→開設届〉で逆算しましょう。
管理者の適法性(資格・常勤・兼務・変更・責務)
管理者は施設に見合う資格者を据える(診療所=医師、歯科は歯科医師)。勤務は診療時間帯を中心に常勤を基本とし、不在時の代行者、緊急呼集、移動手順を体制図に明記。管理者の兼務は原則不可ですが、所轄の許可で無床診療所同士など一定の場合に認められます。
就退任・交代は「変更後10日以内の届出」を失念しないこと。日々の責務(医療安全・感染対策・掲示・従業者監督)は、分院KPI(インシデント、研修、時間外)で可視化し、本院と同水準で運用します。
理事会・社員総会の“形式”を落とさない
分院新設は法人にとって重要な業務執行。理事会では定足数、利益相反の除斥、議決事項の明確化、議事録の記載要件(開催通知・配布資料・賛否・異議)を満たし、必要に応じて社員総会(評議員会)で定款変更を適式に実施。会議体の瑕疵は許認可・登記・融資に波及します。
定款の整備と順序
分院の名称・所在地等を定款に反映。工程は「定款変更(認可)→変更登記→行政手続」が基本。逆転させると差戻しの原因になります。
工程表でクリティカルパスと提出先・期限を可視化しておきましょう。
構造設備・人員は“図面で詰め切る”
無床でも、待合・診察・処置・X線・薬品保管の配置、感染対策、消防・バリアフリー、個人情報/ITの動線設計、医療機器の電源・床耐荷重・遮へい(レントゲンは鉛当量の計算書)が要点。配置換えが効く段階で赤入れを完了させ、管理者・従事者の勤務票や備品表を標榜科とセットで整えます。
事前相談で見取り図や仕様書まで確認してもらうと、工事後の手戻りを防げます。
医療広告(名称・HP・SNS)の落とし穴
比較優良・誇大・体験談の強調は不可。広告可能事項の範囲を守り、症例数・結果などを出す場合は根拠資料の保存と更新ルールを決めます。
院名表記、看板、HP、リスティング広告、SNSを同じ基準で統一し、制作会社にはガイドラインと事前チェックを徹底。ウェブも広告規制の対象である点を忘れずに。
開設後の届出と運用を“回す”
休止・再開・廃止、管理者・標榜科・構造設備の変更など、開設後も期限付きの届出が続きます。
分院ごとにコンプライアンスカレンダーを作り、理事長の定期報告、医療安全・感染対策委員会、内部監査を年次PDCAに組み込みましょう。
診療報酬の手続(保険医療機関指定・施設基準届出)は医療法の許可・届出と“別レーン”で並走させると滞りません。
まとめ
つまずきやすいのは、
①許可・届出の取り違え、
②管理者要件の詰め不足、
③会議体の形式不備、
④定款整備の遅延、
⑤広告表現の過剰、
⑥開設後の届出失念。
対策は、最初に“無床診療所としての適法な型”を固定し、工程・会議体・図面・表示・運用の5軸で前倒しに潰すこと。
定款・議事録・図面・機器仕様・人員体制・広告原稿・届出控を一冊に束ね、「誰が見ても合法」とわかる証拠を用意しておけば、審査も運用も格段にスムーズになります。
⇩