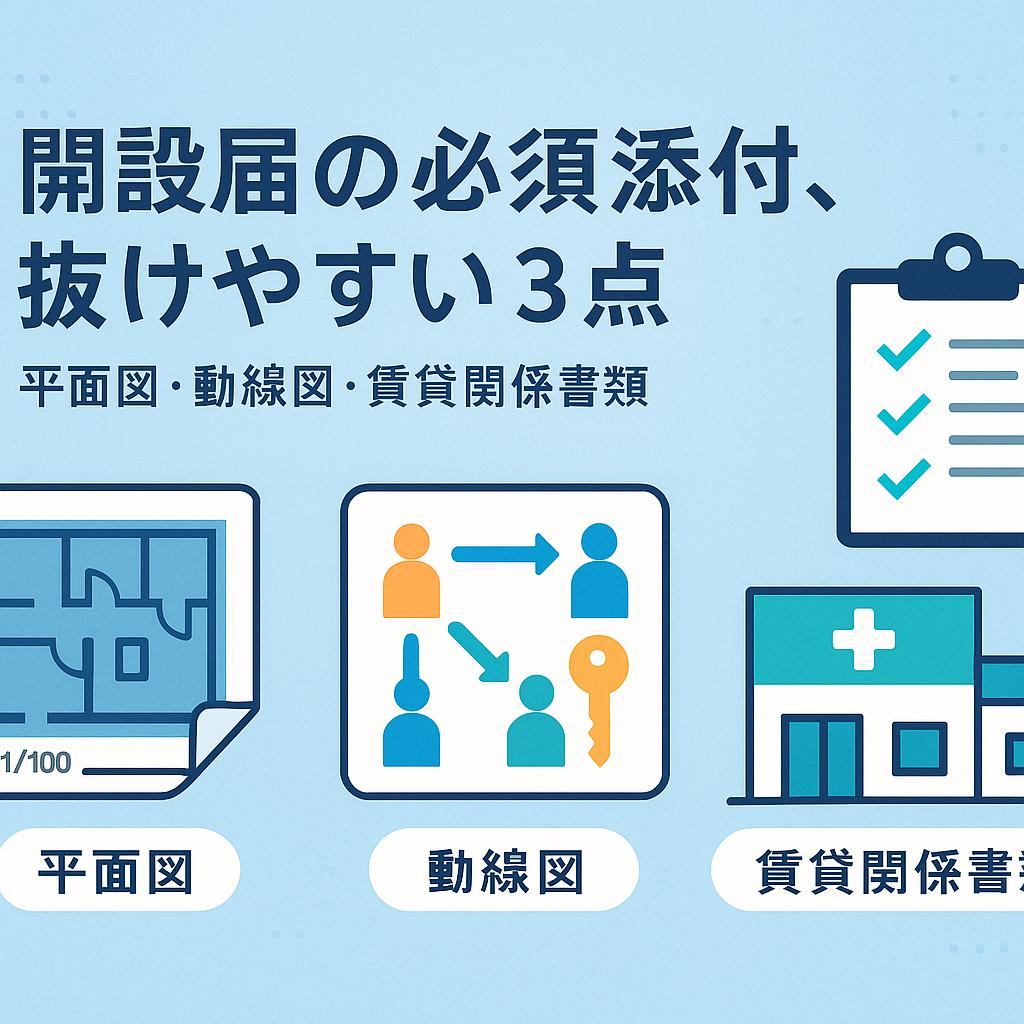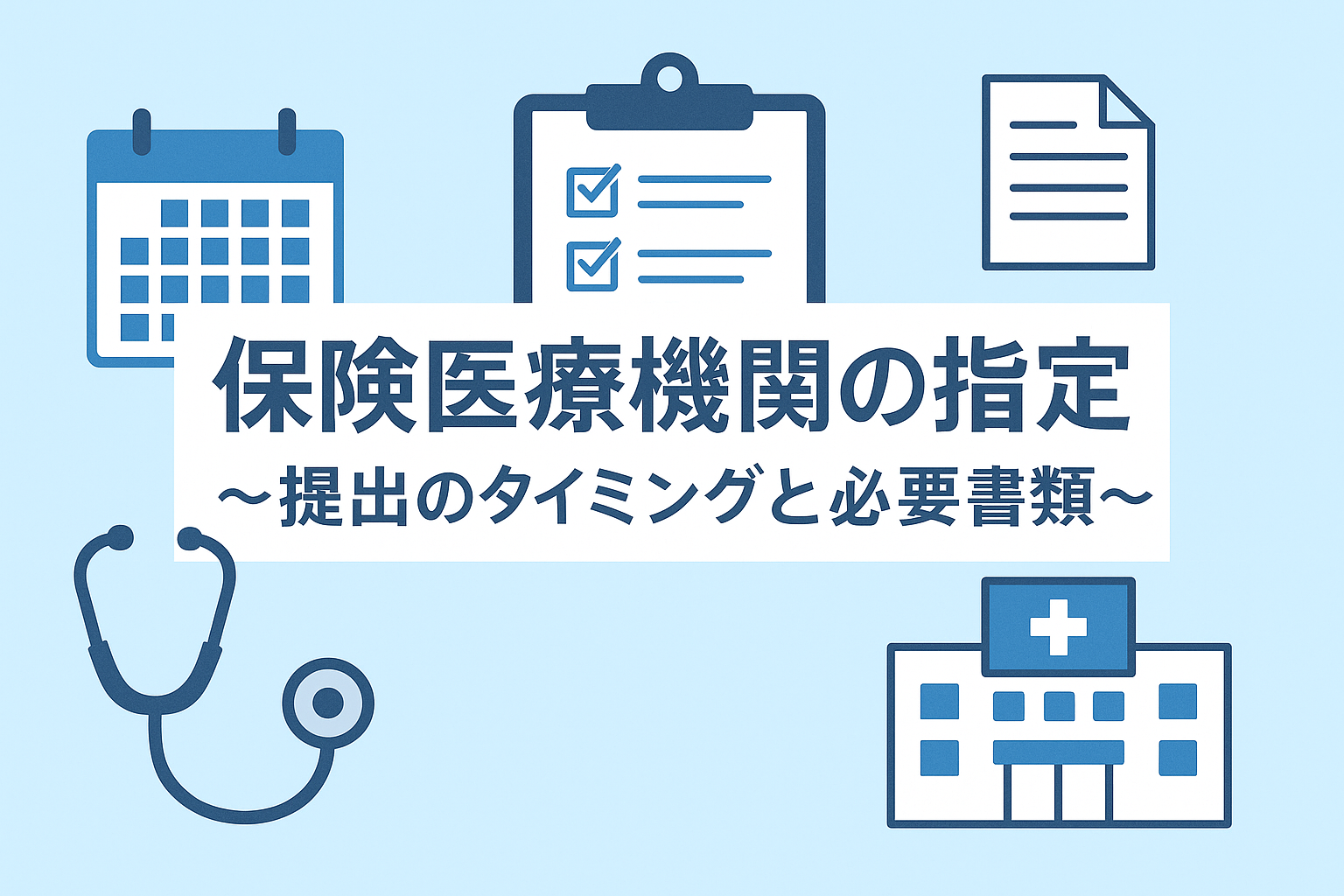
はじめに
個人開業や医療法人化の直後、「いつ、何を出せば保険診療を始められるのか」が最も問合せの多いテーマです。
ポイントは、①医療法に基づく開設許可・届出と、②公的医療保険の「保険医療機関指定」(および③保険医の登録)が別レーンで進むという構造を押さえること。開設が整っていても、指定が下りるまでは保険診療の請求はできません。
以下、実務でつまずきやすい順番と書類を、行政書士の視点で整理します。
提出のタイミング(時系列)
①計画段階
所管庁(保健所・都道府県)と開設手続の要件、厚生局と指定の見込み時期・様式を事前に擦り合わせます。
地域で締切日や必要添付が微妙に異なるため、最初の段取りが肝心です。
②開設許可・開設届
内装・人員・備品の整備、管理者選任、標榜科目の決定まで含めて医療法上の要件をクリア。許可(または届出)の控えが、のちの指定申請の基礎資料になります。
③登記・体制整備(法人の場合)
理事長の代表権、役員体制、基本財産の設定、就業規則・院内規程、事故発生時の連絡体制、個人情報管理等を文書化。名称・所在地・代表者名は後続の全書類に整合させます。
④保険医登録の申請(医師・歯科医師)
勤務医を含め、保険医としての登録を忘れずに。指定と同時並行で進めるのが実務上スムーズです。
⑤保険医療機関の指定申請
開設の根拠書類が出揃い次第、厚生局へ提出。原則として、診療開始予定日から遡って余裕をもって申請します。
指定日は月初付等の運用が多いため、逆算設計が重要です。
⑥レセプト請求の準備
オンライン資格確認、レセ電算、審査支払機関(支払基金・国保連)への新規登録、金融機関口座の名義確認までを同時に。指定通知書の写し提出を求められる場面があるため、受領後すぐ配布体制を。
必要書類(標準的な例)
・保険医療機関指定申請書(指定科目・診療日時間・人員配置を明記)
・開設許可書または開設届の受理書(写し)
・管理者(院長)免許証の写し、履歴書
・勤務する保険医の一覧(勤務形態・時間割)
・平面図(動線・面積・感染対策の概略が分かるもの)
・医療機器・設備一覧(X線、滅菌、救急カート等の主要装置)
・法人の場合:登記事項証明書、定款(寄附行為)、役員名簿
・賃貸物件なら賃貸借契約書(用途・転貸可否の確認箇所)
・標榜科目・標榜医の根拠(学会専門医でなくても標榜可否は別論点)
・医療賠償責任保険加入の有無(任意だが示すと審査が円滑)
・オンライン資格確認の導入計画(システムID・ベンダ情報)
・銀行口座届(名義・カナ表記・フリガナ整合)
施設基準の届出
指定と同時に、各種加算の施設基準を「別紙」で申請するのが効率的です。
例:外来感染対策、在宅医療関連、院内トリアージ、画像診断管理、処方・リフィル対応体制など。図書・マニュアル・研修記録・委員会設置要領・実績要件を証する帳票を準備し、体制整備→文書化→周知・訓練→届出の順で。一部は算定開始月の前月末締切等があるため、カレンダー管理が必須です。
よくある落とし穴
・指定前の保険診療実施(減額・返還のリスク)
・代表者名義不一致(登記・口座・印章・請求システムのズレ)
・標榜科目と算定科目の不整合(広告規制・実態の齟齬)
・保険医登録の失念(勤務医の算定不可)
・オンライン資格確認未整備(加算・算定要件の逸失)
・届出書式の差異(厚生局ブロックごとの細かな違い)
まとめ(実務フロー)
「開設許可/届出 → 登記・体制整備 → 保険医登録 → 指定申請 → 施設基準届出 → レセ関連登録」。この“6工程”を1つのチェックリストで動かし、名称・所在地・代表者・口座・システムIDの“同一性”を通底させれば、指定日=診療開始日にスムーズに接続できます。
締切と添付のローカル運用は事前確認が鉄則。迷ったら、最初に厚生局と保健所に並行で相談し、タイムラインを確定しましょう。
⇩